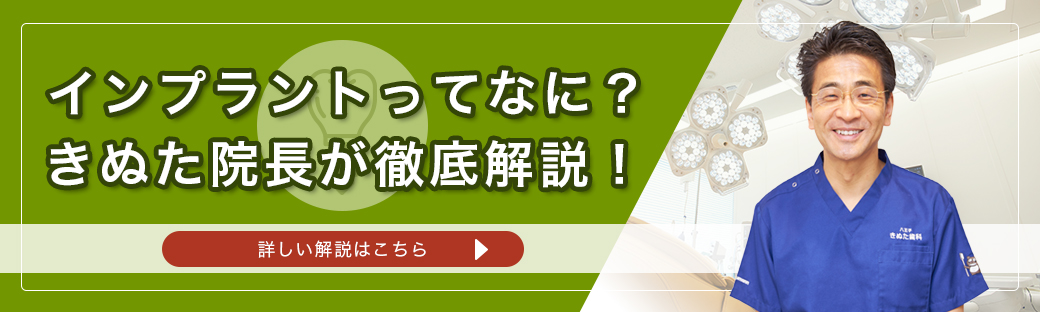GBR法とは
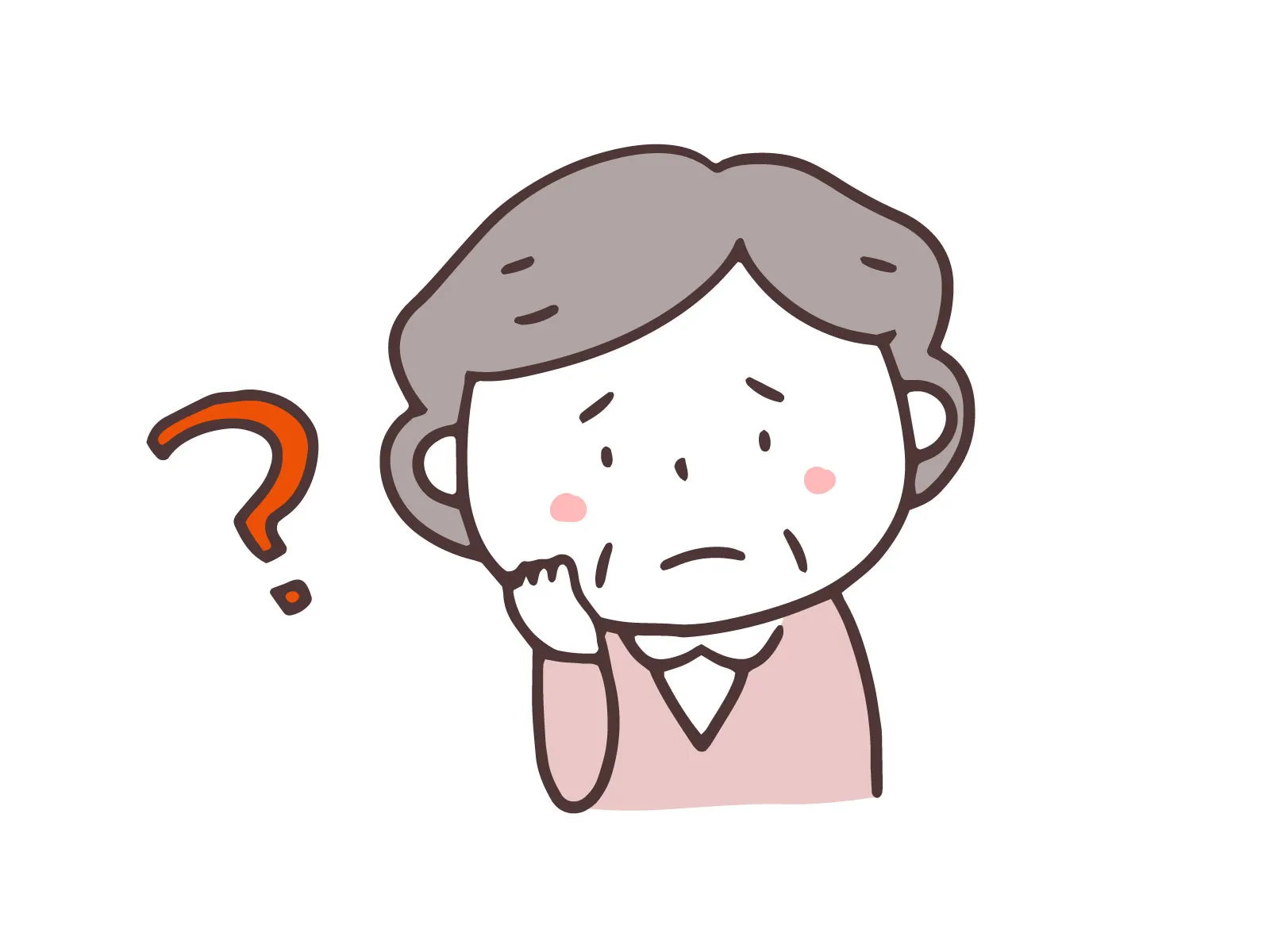
顎の骨の厚みや高さがない場合は、「このままではインプラント治療ができない」と歯科医師に判断される場合があります。
その際に行われる治療法を、GBR法といいます。
GBR法は、骨誘導再生法ともよばれる、骨造成法の1つです。
顎の骨の厚みや高さが不十分な場合に、自家骨(自分の骨)や骨補填材を充填して土台となる顎の骨を補強し、インプラント治療を可能にします。
骨造成については「インプラント治療で聞く「骨造成」とはなんでしょうか?」をご覧ください。
GBR法が必要なケース
インプラント治療では、歯を失った患部の顎の骨に穴をあけて、「インプラント体(人工歯根)」を埋め込みます。
その際に、インプラント体が顎の骨に収まるようであれば、GBR法は必要ありません。
しかし、顎の骨が痩せている、または厚みがない場合は、インプラント体を埋入してもすぐに脱落してしまいます。
GBR法は、インプラント体が抜け落ちるのを防ぐための重要な事前措置なのです。
インプラントの骨造成治療の種類
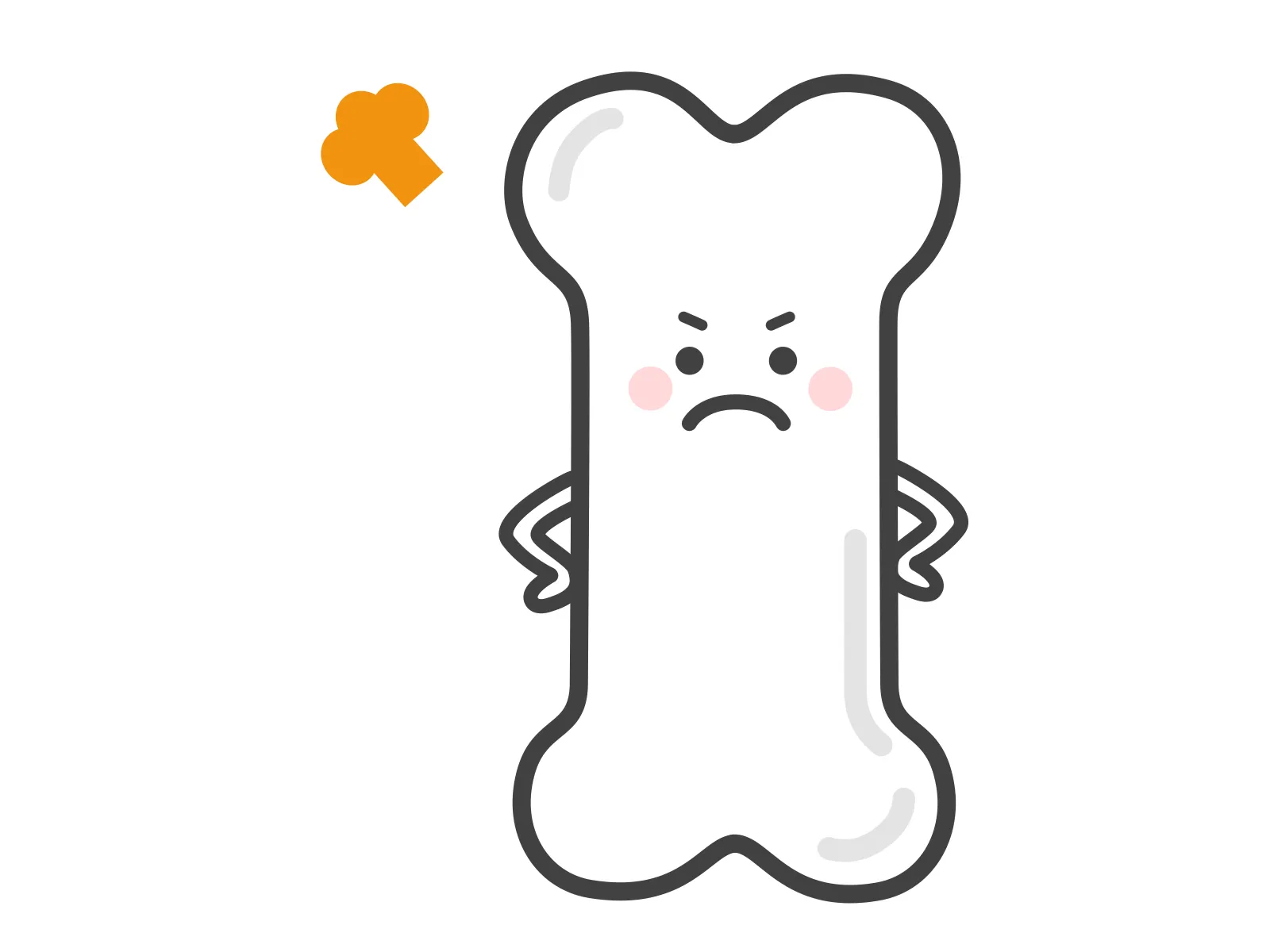
骨造成治療には、GBR法のほかにも「サイナスリフト」と「ソケットリフト」という、2つの方法があります。
それぞれのメリットやデメリットも簡単に紹介します。
サイナスリフト
サイナスリフトは、上顎にインプラント体を埋め込むための十分な骨の厚みや高さがない場合に行う、骨造成手術です。
上顎奥歯の骨の厚みが5ミリ以下の場合に採用され、複数の歯が欠損したときに適しています。
サイナスリフトは、広範囲に骨造成を行うことができるというメリットがあります。
ただし、骨が造られるまで半年程度の期間が必要です。
治療が長期にわたるというデメリットを考慮したうえで、ご自身の状況に合わせて治療を受けましょう。
ソケットリフト
ソケットリフトとは、サイナスリフトと同じく、上顎のインプラント治療に用いられる治療法のことです。
上顎奥歯の骨の厚みが、6ミリ以上の場合に採用され、部分的な骨造成を行う際に適しています。
サイナスリフトとの違いは、骨の造成とインプラント体の埋入を同時に行うという点です。
増やす骨量がサイナスリフトと比べて少ないため、同時並行で治療できます。
治療期間が短く、外科手術を複数回行わないため、身体への負担が少ないというメリットがある反面、デメリットとしては、広範囲の骨造成には向いていない点が挙げられます。
GBR法の費用の相場
ここでは、GBR法にしぼって費用を解説します。
GBR法を用いる場合は、通常のインプラント治療に加算して3万~10万円程度の費用が必要です。
ただし、施術の難易度や患部の状態、歯科医院によっては費用が異なるので、事前に歯科医師に確認してみてください。
GBR法の費用相場については「【GBR法】インプラント治療の骨造成手術にかかる費用の相場はどのくらいですか?」をご覧ください。
インプラントのGBR法治療のリスク

GBR法をはじめとした骨造成治療は、メリットが多い反面、リスクもあります。
ここからは、GBR法についてそのリスクをみていきます。
GBR法のリスク
- 移植した骨の材料が細菌感染を起こす可能性がある
- 通常のインプラント治療よりも腫れや痛みが強く表れる可能性がある
GBR法では外科手術で骨を移植するので、傷口に細菌が入り込んで感染症を引き起こす可能性があります。
また、GBR法の術後には腫れや炎症、痛みなどの症状が強く表れる可能性も考えておかねばなりません。
ですが、こうした症状は長くても2週間程度で落ち着くので、患部を刺激しないように、できるだけ安静にして過ごしましょう。
インプラント手術の痛みについては「インプラント手術で痛みを感じることはありますか?」をご覧ください。
インプラント治療でGBR法を行った際に腫れが起きる原因

インプラント治療でGBR法を行った際に、患部に腫れが起きてしまう原因は、大きく分けて2つです。
原因①免疫反応・防御反応
インプラント治療や骨造成治療は、患部を切開する外科手術の際、傷口を守ろうと免疫反応や防御反応が起きて、患部が腫れる場合があります。
この場合は、患部を安静にしていれば、2週間程度で治まるはずです。
2週間で腫れが治まらないようであれば、何らかのトラブルが起きている可能性があるため、
治療を行った歯科医師に相談してください。
原因②細菌感染
もう1つ考えられる腫れの原因は、先ほども述べた患部の細菌感染です。
インプラント治療やGBR法は、無菌状態の手術室で外科手術が行われますが、感染対策に不備があった場合、患部に細菌が入り込んで術後感染を起こすことがあります。
細菌感染による患部の腫れは、放置すると化膿して膿が出るようになったり、骨とインプラント体の結合を妨げたりします。
そのため、腫れが長引く、症状が悪化するなどの場合は、治療を行った歯科医師に報告しましょう。
インプラント治療後の腫れを軽減する方法
GBR治療後に腫れや痛みが出てしまった場合、症状を悪化させないようにするためにはどうしたらよいでしょうか。
以下に2つの方法を紹介します。
方法①患部を刺激しない
まずは第一に、患部を刺激しないことが大切です。
手術後の傷口は非常にデリケートで、出血する可能性も高いので、手や舌、歯ブラシなどで傷口を触らないように注意してください。
また、食事の際も、患部を避けて噛むよう意識しつつ、噛む力が少なく済むゼリーやおかゆ、スープなどの柔らかいものをとるようにしてください。
方法②処方された薬を指示通り服用する
手術後は、歯科医師から処方された痛み止めや抗生物質などの薬を、指示通りに服用するようにしましょう。
薬の飲み忘れや、自己判断で薬の服用をやめると、症状の悪化につながります。
万一、処方された薬を指示通り服用しても、腫れが長引く、もしくは痛みが軽減しない場合は、薬では治らない深刻なトラブルが起きている可能性があります。
そのような場合には、できるだけ早く、治療を行った歯科医師に相談することです。
GBR法を行ったあとに腫れや痛みが長引く場合は歯科医師に相談しましょう
今回は、GBR法を用いてインプラント治療を行ったあとの、腫れや痛みなどの症状を詳しく解説しました。
術後に腫れや痛みが起きてしまった場合は、様子をみながら、治療後の過ごし方に気を遣う必要があります。
もし腫れや痛みが長引く場合は、患部にトラブルが起きている可能性があるので、治療を行った歯科医師に相談してください。
当院では、患者様が安心してインプラント治療を受けられるように、治療前に十分な説明を行い、細心の注意を払って施術を行っています。
「インプラント治療 を受けたいがいろいろと不安」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。
この記事の監修者

日本歯科大学新潟生命歯学部を卒業後、インプラント治療に従事。現在では年間3000本以上のインプラント治療の実績がある。
日本でインプラント治療が黎明期だったころからパイオニアとして活躍し、インプラントメーカーのストローマン社やノーベルバイオケア社から公認インストラクターの資格を得た。
本の執筆やTV・雑誌などのメディア出演、自身のYouTubeチャンネルなどで情報発信を積極的に行っている。
<主な著書>
インプラント治療は史上最強のストローマンにしなさい!!
歯医者が受けたい!インプラント治療
あっそのインプラント、危険です!!
<YouTubeチャンネル>
八王子きぬた歯科
<外部サイト>
きぬた 泰和 Wikipedia